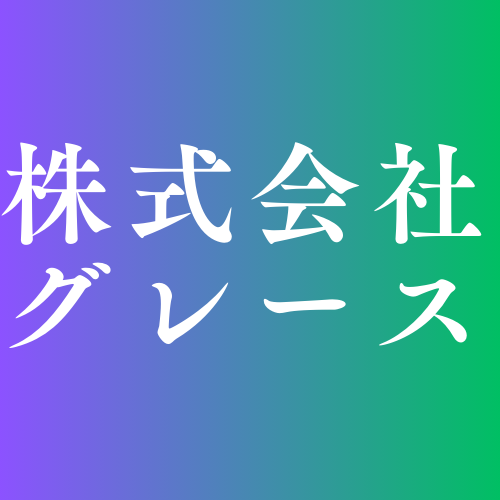主に群馬県内でのお葬式の習慣やお役立ちいただける情報を掲載しております
新生活とは
群馬県に残っているしきたりの一つに「新生活」という香典があります。
群馬県の葬儀では、受付が「一般」と「新生活」に分かれていることもあります。
では「新生活」とは何なのかと言いますと「香典返しは必要ありません。少額ですが今後の生活の為にお役立てください」という意味合いで渡す香典のことを「新生活」といいます。
戦後間もない頃の日本は皆貧しかったため、冠婚葬祭の費用にも事欠く状況でした。
そうした中、礼儀を重んじつつ香典の負担を軽減する方法として「新生活」という方法が生まれたと言われております。
つまり、生活が苦しい中でも日本のしきたりとして礼を尽くす意味で香典を渡さないという選択は出来ないので、少額の香典を渡す。
ただ、一般的な香典よりも少額となるので香典返しは不要ですという新しい香典を考え、これを「新生活」と呼んだのです。
市町村などの行政機関もこの「新生活運動」を推進したことで、無礼な方法ではないということになり、皆が安心してこの「新生活」を行うようになっていきました。
時代が移り変わり、経済成長により日本が豊かになってきて多くの地域でこの「新生活運動」は下火になっていきましたが、
一部の地域では未だに残っており、群馬県の多くの地域でも「新生活運動」がまだ残っております。
市町村のwebサイトなどでは未だに「新生活運動」が推奨されていたりもします。
喪主側としても、香典を頂いてもお返しに半額程度の香典返し(物品)を渡すということで、結果的に金銭はいただいた香典の半額程度にしかなりませんので、喪主側にとっても参列者にとっても都合の良いものなので続いているのかもしれません。
新生活の香典
実際に「新生活」はどのように包んだらよいのかというと、普通の「香典」「御霊前」の包みの表側の左側などに縦書きで
「新生活運動の趣旨に従い香典返しを辞退致します」などと書くことで、これが「新生活の香典」となります。
金額は1,000円から3,000円が一般的です。
※「新生活」受付で5,000円以上のお香典を渡すと、かえって受付係を困惑させてしまうので、避けたほうが無難です。
しかし他の地域から参列する方は、無理に合わせる必要はありません。
「一般」受付であれば高額のお香典でも問題ありませんし、香典返しも行われるのが通例となっています。
故人との関係性から、5,000円以上のお香典を出したい場合は「一般」受付を利用しましょう。
「新生活運動の趣旨に添ってお返しを辞退致します」とか、単に「新生活となります」などと一言添えて受付に出します。
昔は、最初から印刷してあるものがありましたが、最近はホームセンターや文具店などで印刷してある新生活用のものを目にすることが少なくなってきました。近年は、群馬県でも「新生活」というものが馴染まなくなってきているのかもしれません。
ただ、「新生活」と言えば意味が通じますので、「香典返しは不要です」ということで「新生活」を利用するのは、群馬において全く問題ございまん。
「新生活」の場合
参列者様は、お返しを辞退し、礼状のみ受け取るようにしましょう。
喪主様は会葬の御礼状を用意し、お返しはお渡ししないようにしましょう。
群馬県の葬儀では、受付が「一般」と「新生活」の2つに分かれているケースが少なくありません。
「新生活」と書かれた受付は、「新生活運動」の趣旨(しゅし)に賛同される方用の受付で、こういった形式の葬儀は
「生活改善方式」「公民館方式」などと呼ばれているようです。
隣組(となりぐみ)・隣保班(りんぽはん)・勝俣班(かつまたはん)
かつての日本には、近隣住民の相互扶助組織が町内会の中にあり、地域によって「隣組(となりぐみ)」や「隣保班(りんぽはん)」などと呼び習わされてきました。こういった地域コミュニティを九州地方では「勝俣班(かつまたはん)」と呼ぶ習慣がありますが、長野県と群馬県にも同様の呼び方をする地域があります。
組内に不幸があった場合は、遺族に代わって「隣組」が葬儀を取り仕切ることもあるようです。
こういった地域コミュニティは、地方でも都市部を中心に減少傾向にありますが、群馬県では都市部でも機能しています。
忌中告知
群馬県では忌中告知の方法として「竹竿の先に位牌を結び付けたものを門前に立てる」「臼(うす)の絵を描いた半紙を横に倒して貼り付ける」
といった慣習があるようです。臼は横にしては使えないことから「喪(も)」を表現しているようです。
臼を用いた葬送習慣は他にも存在しますが、その由来については諸説あるようです。
臼はもち米を搗いて(ついて)餅にするための道具ですが、搗きたての餅の白い色が浄化(じょうか)の力をもつからという説もあります。
かつては、不幸があった家の玄関に貼り付けられた「忌中札」ですが、近年では見かけることも少なくなっています。
上記のような葬送習慣は、徐々に少なくなっているようです。